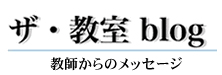« 2004年08月13日 | メイン | 2004年08月15日 »
ケアリング

私が常任委員をつとめている全国生活指導研究協議会では、機関誌として「生活指導」という月刊誌を明治図書から発行しています。昨日はその編集委員会でした。1月号、2月号の編集と、10月号に掲載予定の竹内常一論文についての学習をしました。
竹内論文は、今の子どもたちは「『この自分を引き受けて生きることのできない』と泣き叫んでいる」といった衝撃的な結論から始まっていました。
そしてそれは、「子どもたちははじめから『自分である』ことをやめさせられてきたからである」とし、その叫びは「『この世界を引き受けることができない』という叫びでもある」としています。ゆえに「子どもたちからすれば、自分を引きさき、自分であることを妨げてきたこの世界に敵意をもつことはあっても、それに責任を持つことなどありえない。だから、世界になにが起ころうと、子どもたちには『関係ない』のである」「それなのに、親や教師たちは社会的な約束事をまもり、現実の世界に応答することを求めてくる。そればかりか、それをまもらず、それに応答しないことをすべての罪悪のようにいう。かれら・彼女ラニハソレガ『ウダイ』(ママ)のだ」と。
それではなぜ子どもたちは自分や世界を「引き受ける」態勢を自己の中につくりだせなくなったのでしょうか。
竹内氏は、芹沢俊介の「イノセンス」(純粋・無垢・無罪・潔白)を引用しながら、子どもたちが「イノセンス」から自己を解放し、強制された不自由を自ら選びなおす過程での「対抗暴力」を親や教師が認めず、抑圧しているからであるとしています。
芹沢俊介によると、子どもはある親の子として強制的に産み落とされたものであって、自分から選んで生まれてきたわけではなく、そのかぎりでは、子どもは自分に責任のない、根源的に受動的な存在、「イノセント」な存在であるといいいます。そして子どもはこの強制された不自由を自ら選びなおし、その過程で「対抗暴力」を展開しながら「このままでは現実を引き受けられない」というメッセージを表出しているといいます。そして親や教師がこの「対抗暴力」(ありのままの自分を受け容れてほしいという願い)を受け容れないがゆえに、子どもたちは「自分を引き受けて生きることができない」「世界を引き受けることができない」という思いにとらわれ、反抗・拒否・撤退をエスカレートしていくと論文では述べられています。
さて、それではどうして親や教師は子どもたちのこういったメッセージを受け容れられなくなったのでしょうか。
竹内氏はこの件に関して口頭で、「日本の大人の『こわばった顔』」という表現で説明してくれました。
この「こわばった顔」とは、戦時中の兵士の顔であり、高度成長期のモーレツ社員の顔であり、今の「教育家族」の母親の顔であると。そしてしおちゃんマン的には、「成果主義」に負われるであろう、21世紀の教師の「顔」であるかもしれないと思いました。
そして今、親や教師に求められことは、なによりもまずかれ・彼女のそばにいて、かれ・彼女の声を「聴く」ことであり「配慮し、応答し、世話をする」すなわち「ケア」することであるとしています。
このケアリングについては、感情の押し売りとしての「投げ入れとしての共感」ではなく「受け入れとしての共感」が大切で、その「受け入れとしての共感」とは、親や教師が「自分自身が変容されることを許して」おくものではなくてはならず、そのことを通じて「自分の思い込みや思いあがりから」向けだすものでなくてはならないとしています。
さらには、「ケア」が他者の苦境を引き受け、他者と共に苦闘するものである限り自分自身を危機にさらすことになるがゆえに、「自己のケア」が大切であるとしています。つまり、他者のケアに走るあまりに、自分の精神を他者に預けてしまう悲惨に落ち込む危険性があるということです。
しかし、竹内氏が提起しているケアとは、自己のケアが大切であり、「つまり『自分を大切にする』ことをつうじて『他者を大切にする』ことに進み出るのであり、自己の自由をつらぬくことをつうじて他者の自由への希求に応答するの」であり、「ケアリングとは、ケアするものとケアされるものとが相互にケアしあうようになる」ことだとしています。
だとしたら、しおちゃんマン的には、このケアする者同士の「距離」が大切だと思いました。
自分が危機にさらされるという危険を感じたときに「ちょっと待って!」と言える「距離」をつくれることが大切であり、一方で、ケアが相互にはたらくものである限り、それはそれぞれが別なつながりを持っていることを意識した、集団的なものであるのかもしれないと思ったのですが、これは今後検討が必要かもしれません。
コメント (0) /トラックバック (0) /wrote by しおちゃんマン
終戦59周年を前に
終戦の日を前に、上記の本を読んでみました。「半落ち」でベストセラーを生み出した横山秀夫氏の本は、氏の警察物が好きですべて新刊で揃えています。そして今回、戦争に関する新刊が出たということなのでさっそく購入して一日で読みきりました。
横山氏は私と同い年。もちろん戦争を体験しておらず「期待される人間像」の文科省の教育方針の下、高度成長期に子ども時代をすごしてきた世代であり、学生運動にも「間に合わなかった世代」です。そんな氏が戦争をどのように総括しているのかに興味がありました。
内容は……、甲子園の優勝投手の並木が「人間魚雷」の搭乗員となることをなぜ受け入れたのか…。そしてそのことを通して、戦争の意味や生きることの意味を問い直そうとしています。
当時の若者が、主人公並木のような社会のとらえ方をしていることに若干違和感がありましたが、生きること・死ぬことの意味を誠実に問い続ける主人公に共感しました。
「命」の大切さを教えることの重要性が叫ばれています。
「命」(生)を教えるということは、(死)は(生)の絶対否定であるという冷厳な事実と、どんなに苦しくつらくてもその人生を生き抜くことの価値を丁寧に心を砕いて子どもたちに教えていかなければならないと思っています。
この本を読んで、ふと、そんなことを思いました。
これはいわゆる「反戦文学」ではありませんでした。
しかし、戦争を個人が生きることの意味として考えさせられる作品で、その一人ひとりが生きることをさえぎる戦争は、絶対に、どんな理由があろうともやってはいけないものだとあらためて思いました。
コメント (0) /トラックバック (0) /wrote by しおちゃんマン